みなさんこんにちは!
現役動物看護師のクロころです。
今回は「うさぎと水分」について解説してきます。
うさぎが生きていく上で、適切な水分補給は非常に重要です。
食事からも水分を摂取しますが、不足したり過剰摂取になると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
我が子の水分摂取量はどうだったか、気になるところはないかを考えながらご覧ください!
うさぎの適正な水分摂取量

まずはじめにうさぎの適正な水分摂取量は、「体重の約10%」が目安とされています。
例えば、1.5kgのうさぎであれば、1日あたり150ml程度の水を飲むのが理想的です。
しかしこれはあくまで目安であり、食事内容や気温、体調、また個体差によっても変動することがあります。
水分摂取量に影響を与える要因
- 食事内容:ペレット中心の食事よりも、生野菜を多く与えている場合は飲水量が少なくなる傾向があります。
- 気温・湿度:暑い時期には飲水量が増え、寒い時期には減少することがあります。
- 活動量:活発に動くうさぎほど水を多く飲む傾向があります。
- 健康状態:病気やストレスの影響で飲水量が増減することがあります。
水の成分で注意すべきポイント

皆さんはうさぎに与える水はどんなものを用意していますか?
当然といえば当然ですが、うさぎに与える水は清潔で安全なものである必要があります。
基本的には水道水でも問題ないとされていますが、含まれている成分には注意が必要です。
特にミネラルウォーターには注意が必要です。
人では体にいい水という認識が多いですが、カルシウムなどの成分が多く含有しうさぎにとっては悪影響となる場合が多いのです。
注意すべき成分
- カルシウム:過剰なカルシウムは尿路結石の原因となるため、ミネラルウォーターを与える際は硬水ではなく軟水を選ぶのが望ましいです。
- 塩素:水道水には塩素が含まれていますが、長時間放置することで揮発します。うさぎはそのまま摂取すること自体は問題とされていますが気になる場合は浄水器を通すか、一度沸騰させて冷ました水を与えるとよいでしょう。
- 糖分・香料:うさぎ用のフレーバー付き飲料なども市販されていますが、糖分や添加物が含まれているものは避けるのが無難です。
飲水量の変化による疾患

実は「飲水量」の変化は様々な疾患のサインになることが多いことを知っていますか?
うさぎの飲水量が大きく変化した場合、以下のような疾患のサインである可能性があります。
飲水量が増える場合
- 腎不全:腎機能が低下すると、体内の水分調整がうまくいかず、過剰に水を飲むことがあります。
- 糖尿病:うさぎにも糖尿病が発症することがあり、多飲多尿の症状が見られます。
- 子宮疾患(メス):特に未避妊のメスでは、子宮の異常が原因で飲水量が増加することがあります。
- ストレスや環境の変化:ストレスを感じるとうさぎは水を多く飲むことがあり、新しい環境に適応するまで一時的に増えることがあります。
飲水量が減る場合
- 消化器疾患(胃腸うっ滞など):うさぎが食欲不振を伴い、水も飲まなくなる場合は、胃腸の動きが悪くなっている可能性があります。
- 口腔内の問題:歯の不正咬合などで口の中に痛みがあると、水を飲むのが困難になることがあります。
- 脱水症状:暑い日や病気による体調不良で脱水を起こし、逆に水をうまく飲めなくなることがあります。
うさぎにおすすめの給水容器

ここからは給水器についてお話ししていきます。
うさぎの飲水には「給水ボトル」と「給水皿」の2種類の方法がありますが、衛生面や使いやすさを考えると給水ボトルがおすすめです。
給水ボトルのメリット
- 衛生的:ボトルの場合はうさぎが水に濡れることが少ないのが特徴です。うさぎが水に濡れてしまうと皮膚炎などにつながることがあるため注意が必要なのです。
- こぼれにくい:皿と違い、ひっくり返して水をこぼす心配がありません。
- 飲水量の管理がしやすい:目盛りがついているタイプなら、一日にどれくらい飲んだかを簡単に把握できます。
給水ボトルの選び方
- ノズル部分が金属製で錆びにくいもの
- 水漏れ防止機能があるもの
- 取り外して洗いやすいもの
一方で、ボトルに慣れていないうさぎは最初うまく飲めないこともあるため、使い始めは注意が必要です。
もしうまく飲めないようなら、ボトルの設置位置を調整したり、皿と併用して慣れさせるとよいでしょう。
まとめ
今回は「うさぎと水分」について解説していきました。
うさぎの水分摂取は、健康管理の重要なポイントの一つです。
体重の10%程度の水を目安にしつつ、飲水量の増減がないかを日々チェックしましょう。
また、水の成分にも注意しカルシウムや塩素が過剰に含まれていないものを選ぶことが大切です。
給水ボトルを使うことで、衛生的かつ管理しやすい環境を整えることができます。
うさぎの健康を守るために日々の飲水量を観察し、異常があれば早めに対処するようにしましょう!
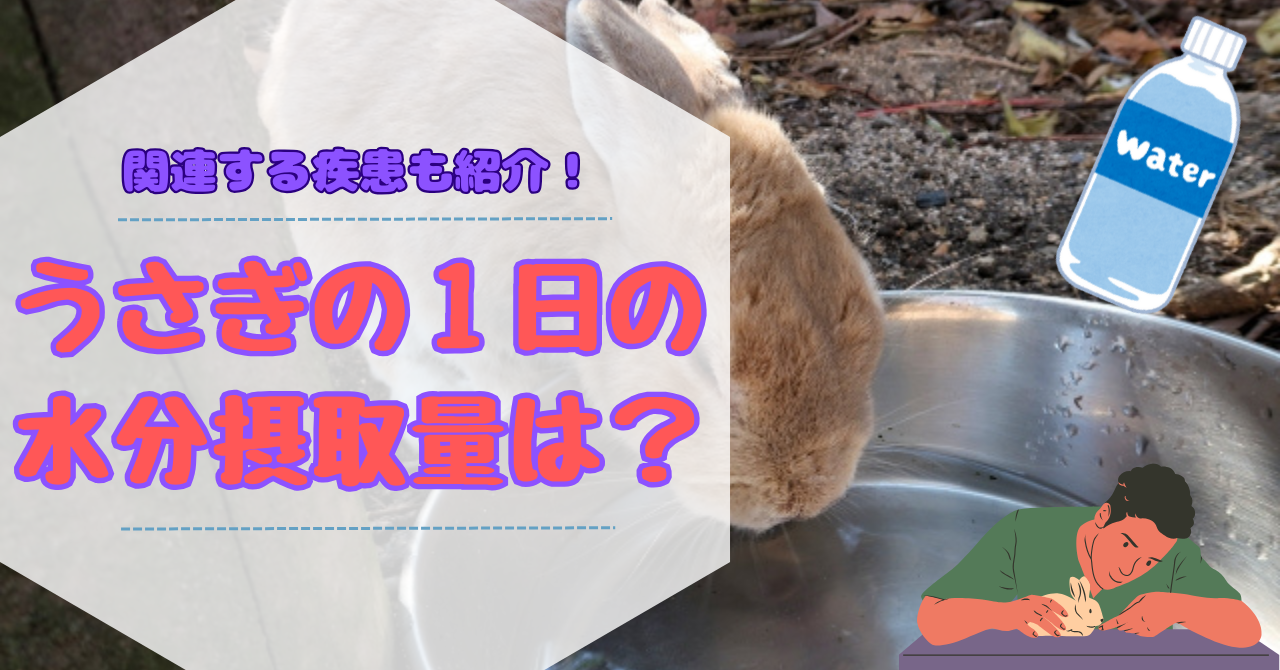


コメント